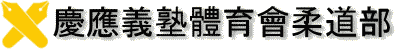お世話になっております。
経済学部3年の長谷川大雅です。
期末試験も終わり、一息ついたと思いきや慶應杯準備に明け暮れる今日この頃でございます。
さて、年が明けて1月以上が過ぎており2月って何か特別なイベントがあるのかと言われるとぱっと思いつかないなという印象があります。
その上で考えてみると、節分があった事を失念していました。幼い頃は、両親や学校の先生から悪い鬼をやっつけるために、豆を投げて年の数だけ豆を食べると良い事が起こるといった縁起を担ぐといったイベントというイメージでした。ただ、ここで考えた疑問としてそもそも年の数だけ豆を食べるのはいくらなんでもハードすぎる点とこの節分というイベントの起源はどのような点があるのかといった事です。
調べてみると、節分の起源は、立春に最も近い新月を元旦とし、新年の始まりである事から立春の前日に節分の行事が行われるようになったそうです。また、節分は邪気払いとして考えられている行事であり、季節の変わり目は邪気が入りやすいという観点から1年間の無病息災を祈る行事として追儺(ついな)と呼ばれる行事が行われたそうです。
元々の発祥は中国でしたが、大陸文化が広く取り入れられていた平安時代、大晦日に宮中行事として疫鬼払いとしての記述が残っているそうです。この宮中行事は江戸時代に行われなくなりましたが、追儺は豆を撒いて鬼を追い払い無病息災を願う”節分”という行事へと庶民の間に広まっていったそうです。
また、豆を撒くようになった理由として、豆🟰魔目(鬼の目)を滅ぼすといった由来から豆は五穀の象徴であり、農耕民族であった日本人はこれらに神が宿ると信じてきたそうです。
さらに、豆を撒く時の声掛けも地域によって千差万別であり、福は内のかけ声のみである地域や鬼は内と良い鬼も存在するからそれを呼び込もうといったユニークな考え方の地域も存在するんだとか。
豆以外にも節分では恵方巻きを食べる文化が象徴的となっておりますが、こんにゃくやけんちん汁や鯨といったあまり聞き馴染みのない食べ物を食べて節分を祝う地域もあるんだそうです。恵方巻きと豆だけに囚われていた私にとっては新たな発見となった一日でした。
このように、かも当たり前のように行事として受容している行事のルーツを知るのも一つの学びになると感じました。
そろそろ増量のための夜食の時間になりますのでこれにて失礼致します。
MENU
部員日誌