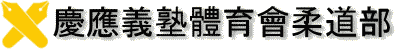お世話になっております。商学部二年の大月楓です。
体にまとわりつくようなジメジメとした熱気が体力を吸い取り、少し動くと滝のような汗が吹き出す。いよいよ本格的に梅雨模様ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
ただいま反転術式により冬を迎えております六徳舎よりお送りさせていただきます。
六徳舎の特徴として過剰な空調により反転する季節が挙げられますが、この蒸し暑い季節に寮内ではベンチコートを着る人も見かけます。私は今部屋に1人なのをいいことに冷房キャンセル界隈を満喫しております。
さて、本題に入ります。
先日深い話をこよなく愛する一年の真田優誠と、「性善説と性悪説」について話しました。
真田に性善説と性悪説のどちらの方が適切だと考えるか問われ、私のその時簡潔に、どちらも好きではない。そもそも二元論が好きではない。と答えました。その時はあまり時間がなくそれ以上の回答ができなかったので、ここで二元論を簡潔に批判してみようかと思います。
まず、二元論の最大の問題は、複雑で連続的な現象を恣意的に切り分けてしまう点にあります。精神と物体、理性と感情、善と悪、自然と文化――これらすべてがしばしば二項対立として理解されてきました。しかし現実には、これらの区別はしばしば曖昧であり、相互に交錯し、連続しています。たとえば感情は身体的な反応と密接に関係しており、純粋な「精神的」活動として分離することはできません。また、文化と自然に関しても、これらは互いに交錯しており、境界を定めることなど本来は不可能であるはずです。二元論的思考は、こうした複雑な相互依存性を見逃し、物事を単純化してしまうことが多々あります。
さらに、二元論はしばしば価値判断と結びつくことによって偏見を助長してしまうことがあります。精神は高貴、身体は卑俗、理性は優れており感情は劣る、文化は先進的で自然は発展途上、男性は理性的で女性は感情的――このような価値の偏重は、差別や抑圧の正当化に使われてきた歴史があります。特にジェンダーに関する二元論的思考は、現代社会における多様な生き方を否定し、固定的な役割を押し付ける温床となっています。このような思考法は、個々人のアイデンティティを狭く規定し、多様性や変化を受け入れる柔軟性を欠いています。
では、二元論に代わる思考法とはどのようなものでしょうか。それは、物事の連続性、相互依存を重視する非二元的な視点であることが絶対条件となります。東洋古来の思想には、こうした観点から物事を捉える試みがなされているものがあります。たとえば仏教における根本的な教えに、「縁起」がありますが、これはすべての存在や現象が、様々な原因や条件によって生じ、互いに関係し合っているという考え方です。単独で存在するものはなく、常に他のものと関わり合いながら変化していくことを示しており、独立した実体としての「精神」や「身体」を想定していません。
結論として、二元論は一見明快に世界の整理整頓する方法を提供しており合理的な思考ですが、その単純さゆえに現実の多様性や複雑さを見逃してしまうという問題点があります。デカルトが二元論を提唱した17世紀は宗教的な世界からの脱却を目指していた為、物事を合理的に捉える必要がありました。しかし現代においては、相互に連関するダイナミックな関係性を前提とした、物事の複雑性を許容する思考こそが求められています。私たちは、白黒ではなく、グレーゾーンの中に真理を見出す感性を育むべき時代に生きているのです。
稚拙な文章になってしまいましたが、ご精読ありがとうございます。
正解のない話題について語り合う。とてもエネルギーを使いますが、たまには楽しいものです。思考能力の劣化を食い止めるべく、日々色々な物事に対して疑問を持ちながら生きていきたいと思いました。
厳しい暑さが続きますが、くれぐれもご自愛専一にお過ごしください。