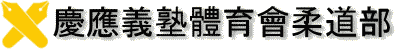僕は僕である。
最近つくづくそう思うのです。
どうもご無沙汰しております。法学部政治学科2年木下魁人です。
バイト先でレジをよく担当するのですが、この際、社会というものを本当に感じられるのです。
というのも様々な方と関わる機会に恵まれるからです。
丁寧に対応してくれる人、1枚壁を作る人、塩対応な人、タメ口であたかも自分がパートよりも偉いと思っている人などなど様々です。
壁を作ったり、塩対応になることは全く問題ないのです。正直その気持ちは分かりますし、大前提として、ただのお客と店員の関係であり、別に彼らと関係値を作りたいわけでも、仲良くなりたいわけでもないからです。
しかし、丁寧に対応してくれるお客さんに関してはとてもありがたい。
「いらっしゃいませこんにちは!」という店員の定型句があります。それに対して、「こんにちは!」と返してくれる方、ありがとうございます。このような方と出会うと、とても嬉しいですし、心の余裕というものを感じる気がしてとても感心します。
他にも、目を見て丁寧な言葉遣いで注文してくださる方や、焦らないでゆっくりでいいよなどと言ってくれる方、ちょっとぶっきらぼうだけどリスペクトを感じる方などがおり、社会も捨てたもんじゃないなぁと心から感じます。
その一方、タメ口で偉そうに対応してくる方に出会うと哀しくなります。何が悲しくて店員に対してあのような対応をするのでしょうか。
「お客さんは神様だ」この言葉を額面通りに受け取ってしまっているのでしょうか。
海外のコンビニの店員などは驚くほど適当で、お客と店員が対等に渡り合っています。
これが100%正しいと主張したいわけではないですが、正直お互い一個人であるわけだから、その関係にリスペクトを欠くことはナンセンスではないでしょうか。これ以上言うと、互助の日本社会をだめにする個人主義を持ち込もうとするなと言いがかりをつけられそうなのでここらでやめておきますが。
とにもかくにも、いろんな人いるな、そう感じる日々です。
また、外国の方と関わると、その感覚がさらに強まるのです。まあ、外国の方は、その人の特徴というより、国民性といったほうが正しいかもしれません。
以前インドの方と関わった際、彼は予定時間に遅刻してきました。
連絡すると、あと5分で到着すると言うのです。しかし、いくら待っても現れないのです。30分後に再び連絡すると、またもや、あと5分と伝えてきました。しかし現れません。結局彼が現れたのは、約束の1時間30分後でした。
本当にいろんな人いるな。
さて、いろんな人に出会った私ですが、その経験により自分が変わったかと聞かれると、全くそうではないように感じます。
人は経験を経て成長する、人との出会いにより成長すると言われます。
もちろん、それらにより自分自身を根底から変化させる人もいるでしょう。しかし、それは多大なる努力と犠牲の上に成り立っているものなのではないでしょうか。人との出会いや海外への渡航により、新たな知見を得て、考えが変わることこそあれど、奥底に根を張っているもの、それが人間性なのか倫理道徳観なのかはわかりませんが、土台が変わることはないのではないでしょうか。
その土台こそが、”自分”と呼ばれるのかも知れません。
人と会うと刺激的だが、一人になると安心する。外国にいくと魅力的に見えるが、日本に帰ってくると安心する。これらはすべて関係しているように思えます。
結局”自分”というものを人は変えていくことはできないのかもしれません。
そもそも、獲得した知見すら、”自分”により受け取られているため、ファーストタッチでバイアスがかかっているでしょう。そうなると、変えられる部分であるはずの、知見に基づく何かに対する考え方さえ、潔白ではないでしょう。
だからこそ、”僕は僕である”とつくづく思うのです。
新しいことに挑戦しても、何をしても、そこには僕がいて、それを受け取るのも僕。
自分を変えたがるのも、自分を型から抜け出せなくするのも僕。最高の伴走者にも、十字架にもなり得る僕。ずっとそばにあるのに、探し求めてしまう僕。
どうあがいても、鎖が軋む音しか聞こえてこない気がします。
「それが僕らしくて殺したいくらい嫌いです」
この歌詞は、まさにぴったりではないでしょうか。
その一方で、生まれた瞬間から”自分”を持っている人などいるわけがありません。では、何が”自分”を形作ったのかと聞かれると、今までの人生経験としか答えが思いつかないのもまた事実。
結局は、探すだけ無駄なのかもしれません。
しかし、プレスター・ジョン伝説が如く、大航海の幕開けになるやもしれない。だからこそ、私は探し続けずにはいられない。
終わり