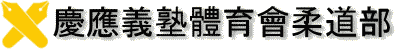こんにちは。真田康志郎です。Jr.大会に一年の時の経過を感じた今日この頃ですが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。私自身肩の怪我により、東京都Jr.には出場することができませんでした。もう出場チャンスがないと思うとやるせないです。去年のこの大会では順調な勝ち上がりだったのですが、駒沢大学の黒川選手に指導で敗れ、試合運びの大切さを実感いたしました。自分の柔道の強みは内股を主軸とする高い攻撃力と相手の技に持っていかれない受けの強さにあります。そんな私が今回東京都Jr.大会に出た慶應の選手の試合それぞれ軽く分析してみたいと思います。
林 鏑木
鏑木はとても体が強く、かつ組み手などの細かな技術が光る選手で林にとって格上です。組み手は左対右で、抱きつきや組み手などで圧倒される試合展開の可能性が高いのでそれを防ぐために長身を生かした立ち回りが要求されました。実際の試合では引き手を取らせずに釣り手で背中を持つという手を取り、格上相手にうまく試合を進めていました。持ち味の前技を警戒させての小外も光ったのですが、引き出しが足りていなく、腰も引けていたため、内股フェイントが相手に効かず、技を決めきれませんでした。結果、有効負けしてしまいました。足を前に出すためにももう少しいい姿勢を取る必要があると思いました。
本吉 大下
右対右の相四つで、お互い引き手を絞り合う展開でした。本吉は序盤から先に引き手を絞っていたものの、相手の引き手のグリップが強かったため吊り手を持っての技は難しいところがあったので、釣り手を対角線で持つという風に途中から戦術を変え、片襟での内股を狙って行ったのは流石の判断でした。釣り手を無理に持ちに行こうとすると、常に釣り手を絞られていたため、その勢いを使われて袖釣りや一本背負などのリスクがありました。相手のサイドへの動きが多く、足が揃うのが怖かったです。最終的に相手を引っこ抜くような内股で一本を取りました。寝技判定か立技判定かの境界線がわかりにくくなった最近らしい一本勝ちでした。
柴田 長田
彼も林と同じ高身長プレーヤーであり、その手足の長さを生かした戦いをすることが勝利の鍵となります。大外刈りと大内刈りを主軸に戦う高身長インファイターのためインファイトとなり、それゆえに距離を詰めに行った時の背負い投げに弱いです。相手は左組で相四つでした。柴田の持ち味を出すためには相手の引き手を落とすというよりは自身の釣り手をあげ相手の頭をコントロールする必要がありました。というのも柴田は背が高いので相手選手の釣り手が柴田の頭をコントロールするのは難しいと考えたためです。結果的に柴田の釣り手が上がった瞬間に大外刈りがしっかりはまり倒すことができました。素晴らしかったのです。ただし、終始ポジショニングが良くなかったので(大内刈り、大外刈りの両方をかけるのに中途半端な相手と遠い位置)改善するとより強くなれると思います。
土川 須藤
左対右の喧嘩四つでしたが、釣り手の差し合いというよりかは前に出ている足の差し合いでした。この状況では足の差し合いも大切なのですが引き手をいかに自分の方に持ってくるかが重要になってきます。内股透かしを双方が狙いつつ、内股・体落としで持っていけるか否かの試合でした。土川の姿勢が狙い技(内股、体落とし)に合っておらず腰が引けていたため最終的に肩車で回されてしまったと感じました。彼の得意技構成的に胸をある程度張って戦った方が強いです。土川は力が強いため胸を張って相手の間合いに入る柔道が似合っていると思います。
真田 飯島
喧嘩四つで背負の掛け合いのような試合でした。両者背負の選手のため釣り手をしたからもち早くに相手制したいところでした。相手の組み手もしつこく、組み手は均衡した攻防をしていました。真田は狙いを内股にシフトチェンジし、上から相手の釣り手を制圧しつつ、逆わざと内股を狙っていました。この釣り手のコントロールは真田が背負をするからこそ背負い投げの選手にとって嫌な位置に置けるのだと思います。本吉同様立ちから寝姿勢に移行する際の内股でポイントを取りそのまま押さえ込みました。
山中 望月
相四つでいかに吊り手を相手に持たせずに絞ることが出来るかが勝負どころでしたが、絞り切ることができず不利な状況での勝負をすることになりました。特にすぐ奥襟をたたかれてしまっていました。そのまま自分の形にすることが出来ずに指導で負けてしまいました。自分と同じまたは自分よりも大きい相手には特に組み手でひとつこだわることが重要でした。今後としては、相四つで対角で釣り手を持って背中を叩かれないようにすることが必須だと思いました。また、いいところを持たれてしまってからの対応を練習するべきだと思いました。
本吉 粕谷
先ほどと同じ右対右の引き手の絞り合い展開になりました。本吉は本線は常に押し続けていました。相手は袖吊りなどの逆回転もできる器用で力のあるタイプでした。どれだけ引き手を絞り切り自分の有利な試合時間を長く展開するかが勝負でした。引き手で釣り手を持って組み手を展開していたのですが相手の切る組手がうまくGSでは劣勢気味でした。本吉の得意の組み手が少なく相手の逆技が審判の好印象を受けていました。釣り手引き手が張っていて全く力が入らない状況で戦い切ったのですが、最後はかけ逃げ指導ということで敗北を期してしまいました。肩襟の内股に持ち上げる力はあるのですが、そこまで脅威でないためバリエーション、または最後まで投げる工夫が必要と感じました。私にもこの技の改善方法がわからないので考えていきたいと思います。
柴田 海堀
左対左の相四つで相手の組手がものすごく上手いです。特に柴田が奥襟を叩きに行った手を押さえるのがうまく、対角線で釣り手を刺して組み手を展開していました。この技術は相手が奥襟を掴んでくるのを防ぎつつ前襟をコントロールすることができます。これの対処法については私の復帰後研究しようと思います。柴田としては奥襟を叩きたかったのですが、相手にコントロールされて叩きに行けなかったです。しかし、途中で海堀の右足を怪我したので棄権して柴田が勝利しました。めちゃくちゃすごいです。
真田 嶋貫
左と右の喧嘩四つでした。嶋貫は背負と巴の選手でした。喧嘩四つのため釣り手の差し合いの攻防があったのですが相手の方が上手で吊り手を真田が後から持つ展開が多くなっていました。近年は特に袖口と対角でのグリップが許可された関係でそれを生かした組手が発展してきています。その対策が今回はできておらず先に釣り手を持たれてしまっていました。真田は組み際の技もうまいためそこを狙ってあえて不利な組み手をすることもあったのですが、今回は単に組み負けだと思いました。相手の背負は威力があるので半身でなければ受けきれず、背負の受けは体制を完全に切って受けていました。そこに逆の一本背負をかけられ飛んでしまいました。ルール改正があったからこそ今は組み手で差をつけることができます。部分練習の必要性を感じました。
山田 川端
左対左の相四つで引き手の絞り合いは互角以上でした。山田は引き手を持ち合った後の切り方がうまく、組み手を有利に進めることができていました。しかし、組み際での怖さを与えるような圧力をかけることができず、相手の反発を使うことが出来なかった結果、得意の一本背負がうまくはまりませんでした。このことが影響して一本背負を返されて技ありを取られてしまいました。圧力は相手に怖さを与え相手の行動を制限するとともに、相手の動きを相手ベースで制御できるのでうまく使えると格段に強くなれます。私もまだうまく出来ないので練習したいです。
柴田 小坂
左対右の喧嘩四つでした。柴田は喧嘩四つの吊り手は上下関係なく技をかけれるので釣り手の差し合いでの攻防は少なかったです。釣り手の圧力もしっかりとかけることができていました。内股と小外刈りが相手に対して有効で、それらを軸にいい試合をしていました。相手の内股に怯むことなく圧をかけ続けたのは良かったと思いました。GSでは相手が内股に慣れてきていたので奥の足を刈りに行く大外刈りに主軸の技を変えるべきであったかもしれません。大外刈りは内股に比べて深く技に入る必要があるため、リスクは大きいですが、柴田の技に対する小坂の体捌きも大きくなります。そこに小外刈りを合わせるのがいいと思いました。また、彼の場合は足が長いため、デメリットは少ないと感じます。
今回の試合を見て今後の課題が見えてきました。一つはルール改正による組み手の発展を追うべきということです。
相四つ
・釣り手での対角線上の差し合い。
・袖口を持たれた時の切り方。
・引き手を先に持たれた時の肩襟対処。
・対角線でつ奥襟対処。
喧嘩四つ
・袖口経由の釣り手の組み手。
二つ目に相手を警戒させることのできる技が必要ということです。最も簡単に相手をコントロールする方法は相手に恐怖を植え付けることだと考えます。技に対する警戒が相手の動きを制限し、圧力を与え、反発を生みます。強くなるには圧倒的な得意技を持っていることは必須条件でありそうです。
最後に
拙い文章をここまで読んでくださってありがとうございます。上記の文章は柔道を今まで以上に楽しむために必要な知識であり、考え方になっていると思います。そのため、柔道に対する解像度がまだ低めの初心者やマネージャーの方に読んで欲しいです。この文章の意味が理解できれば、柔道の美しさをより鮮明に感じ取れるようになると思います。また、私自身が気がつけない新しい発想やテクニックがあると思いますので是非私に自分の柔道理論を教えて欲しいです。